日本海北前シンポジウム報告
「西岩瀬湊を水中考古学で調査する」
|
考古学が明らかにする中世岩瀬湊の実像
|
期日:10月26日(日)
10:00 海禅寺 出発
 海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)
大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。
打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、
仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。
天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”
(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、
富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領
して移転し、現在に至っている。
海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)
大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。
打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、
仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。
天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”
(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、
富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領
して移転し、現在に至っている。
|
10:15 西岩瀬諏訪社
 現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた
西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。
境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。
現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた
西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。
境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。
 享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基
享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基
 西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)
西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)
幹周り約10m、樹高約30m、樹冠の周囲約55mに及ぶ。
樹齢は1000年又は800年と推定されているが、詳細は不明である。
航海の安全を守る聖樹として近郷の人々から親しまれている。
|
10:40 護念山医王寺 海底出土の仏像 見学
 応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、
西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)
越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。
応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、
西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)
越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。
 海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置
されており現物を確認することは出来なかった。
海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置
されており現物を確認することは出来なかった。
|
11:00 四方山大雲寺
中世石造物(石仏・五輪塔)見学
旧神通川右岸辺に立地していることを説明
|

|
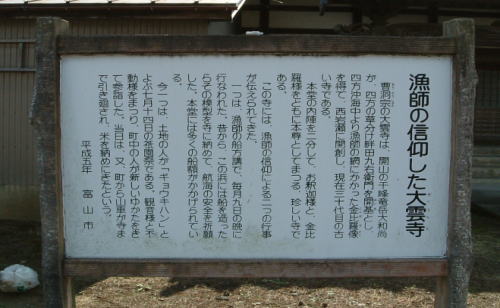
|
曹洞宗派で、四方沖海底から引き上げられた金比羅像を
得た畔田九右衛門が開基したと伝えられている。
境内には一石一尊仏、五輪塔火輪等があり、
これらの石仏は15世紀頃(室町時代)のものである。
|
|
<15世紀頃(室町時代)の石仏>
|
 |  |
|
一石一尊仏
|
五輪塔火輪
|

江戸時代には、現在の四方山大雲寺のすぐ西側を旧神通川(神通古川)
が流れていた。この写真は、旧神通川跡を撮影したものである。
|
|
11:20 打出遺跡
打出遺跡は、打出地内に所在する弥生時代〜室町時代の集落跡である。
集落は、旧神通川右岸の自然堤防上に立地しており、弥生時代から
古墳時代初期の集落は河川跡に面して形成され、中世の集落は河口
から少し内陸側に入った所に形成されている。
発掘調査現場へ行き、中世の屋敷跡(区画された溝、大型井戸)や、
道路跡を見学した。
 中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡
中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡
 中世(12〜15世紀頃)の道路跡
中世(12〜15世紀頃)の道路跡
|
|
11:30 解散
|
11:50 海禅寺 到着
|
13:30 海禅寺シンポジウム
|
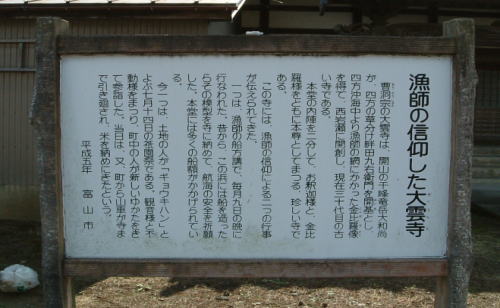
 海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)
大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。
打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、
仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。
天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”
(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、
富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領
して移転し、現在に至っている。
海禅寺(高野山真言宗寺院,本尊:大日如来)
大宝元年(701年)文武天皇の第7皇仏性上人の開基と伝えられる。
打出沖の海中から1尺5寸の黄金の釈迦如来像が引き上げられ、
仏性上人が、打出に七堂伽藍を建立して祀ったという。
天徳2年(958年)に、海岸浸食のために”岩瀬の石の鳥居”
(諏訪社の北と推定される)に移転し、元禄8年(1695年)には、
富山藩2代藩主前田正甫公から岩瀬城本丸跡である現在の地を拝領
して移転し、現在に至っている。 現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた
西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。
境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。
現在は八重津浜に面して存在するが、かつては沖合に広がっていた
西岩瀬町に存在し、宝永4年(1707年)現在地に遷宮したと伝えられる。
境内からは、戦国〜安土桃山時代の遺物(瀬戸天目)が出土した。
 享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基
享和元年(1801年)銘の西岩瀬諏訪社神燈2基
 西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物)
西岩瀬諏訪社の大けやき(県指定天然記念物) 応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、
西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)
越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。
応安元年(1367年)八重津湊の沖で漁師が1尺2寸の薬師如来像を引揚げ、
西岩瀬の東の浜に徳広庵を設けて像を安置した。文明10年(1482年)
越前の護念坊がこの地へきて徳広庵を改め護念山医王寺と称した。
 海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置
されており現物を確認することは出来なかった。
海底から出土した仏像(1尺2寸の薬師如来像)はこの祭壇の奥に安置
されており現物を確認することは出来なかった。




 中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡
中世(12〜15世紀頃)の屋敷跡
 中世(12〜15世紀頃)の道路跡
中世(12〜15世紀頃)の道路跡