(On Dragging Anchor and Grounding of the Training Ship KAIWO MARU)
�C�m��x�R�x��
�@����16�N10��20���A�䕗�g�J�Q�i�ȉ��A�䕗�Q�R���Ƃ����B�j�ɂ�鋭����
�g�Q�ɂ��C���ۂ̑��d�E��g���̂����������B�K���ɂ��A�D�̑����A�d����
�͂Ȃ��l�g���Q�����ōςB�������A�قړ����ꏊ�ŋN�����A�������N 3��
8���ɋN�����^���J�[�̑��d�E��g�C��̂悤�ɓ]�����Ă������S���Ɏ���
���ł��낤�B
�@�C���ۂ́A��X�̃}�U�[�V�b�v�ł���A�Ɨ��s���@�l�q�C�P�����i�ȉ��A�q
�C�P�����Ƃ����B�j�́A�D�����S�^�q�������郁�b�J�ł���B��X�͊C���ۑ�
�d�E��g�����̂ɂ��āA��ώc�O�Ɏv���B�n���x�R�ł́A���̎��̂ɂ���
��X�I�ɒn���̃}�X�R�~�ɂ����Ȃ��ꂽ�B�n���̊C�Z�L���҂Ƃ��Ẳ�
�X�́A�C�Z�ɂ܂������f�l�̈�ʐl��}�X�R�~���猴��������A���̑Ή�
�ɋꗶ�������Ƃ��������B���̎����̌������Ȍ��ɕ\������A�u���ؕx�R�`
�̕x�R���u�d�n�ɕd�������܂܁A�x�R�p�t�߂�ʉ߂����C����䕗������
�������Ƃ͕s�K���Ƃ����A�����̑D���B�̏펯���A�C���ۑD�����m��Ȃ������A
�܂��́A�m���Ƃ��Ēm���Ă��Ă��A�����������ӎu���肪�o���Ȃ�����
���Ɓv�A�u�\�z���͂邩�ɒ������C�ہE�C�ۂł��������Ɓv�A�y�сu�䕗��
������̑D���ɈςˁA���ʑ䕗��ɌW��w�j�݂͐��Ă͂��Ȃ��������Ɠ��A
�q�C�P�����̈��S�Ǘ��̐����s���ł��������Ɓv�ł���B
�@�{���́A�n���C�Z�L���҂Ƃ��đf���ɍ���̒n���C��̍Ĕ��h�~�̂���
�ɁA�x�R�`�ł̊C���ۍ��ʎ��̂ɂ��ď��_�ɂ܂Ƃ߂����̂ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j
�@�x�R�`���ɒ┑���Ă����q�C�P�����̗��K�D�u�C���ہv��2004�N10��20�� ��A�䕗23���ɂ��ϑ��j�������Ȃ��k������̖\���Ɋ������܂�A���d ���ĕx�R�s�̕x�R�`�h�g��ɍ��ʂ����B��g���y�ю��K����167�l��21��15 �����܂łɃw���R�v�^�[��h�g��ƊC���ۂƂ̊ԂɃ��[�v���ċ~�����u �Ŗh�g��ɓn�铙�̎�i�ɂ��S���~�����ꂽ�B�K�����҂͂łȂ��������A 18�������܂Ȃǂ̂��������B �@���̎��̂̏ڍׂɂ��Ă͉��l�n���C��R�����̊C��R���ٌ��^�ɕ� ����Ă���B


�䕗�Q�R���͕x�R���ł͂܂�Ɍ���\���������炵�����Ƃ���A���̊C�� �ۂ̑��d�E��g�������łȂ��A�x�R�����̊e���ɑ傫�Ȕ�Q�������Ă���B ����ɂ��āA���ɕ��A�g�ɂ��āA�n���̋C�ۑ�A�`�p���������̎��� �f�[�^����ɁA�n��̓��F�����l�������������L���B
�@�C�ے��ł͓��{�S���ɃA���_�X�ϑ��Ԃ�z�u���āA�����������܂߂��C
�ۂ̏펞�ϑ����s���Ă���B���ؕx�R�`���ӂ̃A���_�X�|�C���g�͐}3.1
�Ɏ����X���A���A�x�R�A���ÁA�ł���B�܂��A���}�Ɏ����x�R���D����
���w�Z�̗ՊC���K��i�ȉ��A�x�R���D���K��Ƃ���B�j�ł��Ǝ��ɕ����E
�����̏펞�ϑ��y�ыL�^���s���Ă���B���}�ɂ́A���ꂼ��̈ʒu�y�э�
�x�A�����E�����v�̐ݒu���x�������Ă���B�܂��}3.2�Ɏ����Ă���̂́A
�y�����R�[�_�ŋL�^���ꂽ�A�x�R���D���K��ɂ����镗���E�����̊ϑ�
�f�[�^�ł���B�����̕��������v�͊C�ݐ������500m�������ɂ��邪�A
�ݒu�������C�ʏ��30m�ł���A�r���ɕ��ɉe����^����傫�Ȍ�������
�������߁A�C�ݕ��ɂ�����f�[�^�Ƌ߂����̂ł���Ǝv����B�א��̘A��
���u���l�ŁA�������̑������ړ����ϒl�������Ă���B�܂��A�����̋L�^
��30m/s�A90m/s�����W�̎����؊����ł���A�����������Ȃ���20����17��
����21����2���܂ł�90m/s�����W�ƂȂ��Ă���B�����ŋL�^����Ă����
��u�ԕ�����20����20��������42.1m/s�ł���B�����Đ}3.3�͐�ɏq�ׂ�
�R�ӏ��̃A���_�X�f�[�^�i�C�ے�HP[1]�Ō��J����Ă���B�j�ƕx�R���D
���K��ł̊ϑ��f�[�^��̎��Ԏ��i10/20��9������10/21��9���j�Ɏ�
�������̂ł���B�����ŁA�A���_�X�̃f�[�^�͖������O10���Ԋϑ��̕��ϒl
�ł���B�x�R���D���K��̃f�[�^�̕��ϒl�͓��l�ł���A�ő�l�͖������O
��1���ԓ��ɂ�����l�ł���B���̐}���䕗�Q�R���ɂ�����\����́A��
���I�ɂ͕��ؕx�R�`���A���ԓI�ɂ�20���̖�Ԃ�21���O�オ�s�[�N�ł���A
�e�n�ɂ����Ĉ�v���Ă���X���ł���B�����������ۂ͑䕗�̎��ԓI�Ȕ��B
�x�����ƁA�x�R�p���͂̒n�`�����ʂɂ����̂Ǝv����B����ɑ��闝�_
��͓I�ȃA�v���[�`[2]���i�߂��Ă��邪�A�����ł͋q�ϓI�Ȏ������q��
����B�@
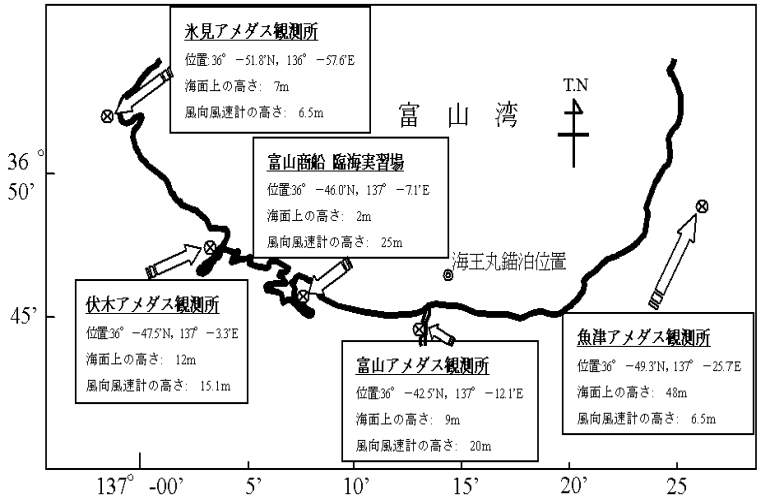
�}3.1�@�X���A���A�x�R�A���ẪA���_�X�A�x�R���D�������w�Z�� �@�@�@ �ՊC���K��ϑ��ʒu �@�@�@�i�A���_�X�̈ʒu�ƍ����͋C�ے�HP[1]�ɂ��j
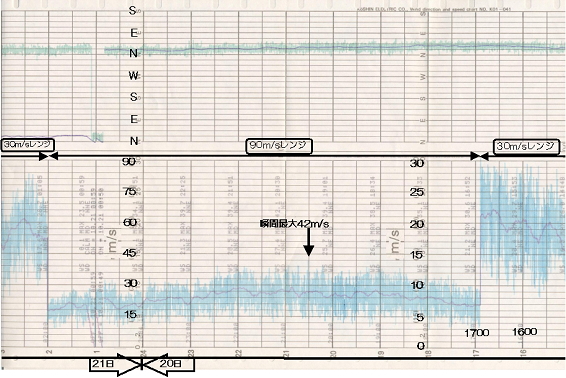
�}3.2�@�x�R���D���K��ɂ����镗���E�����̊ϑ��f�[�^ �@�@�@�i�א��̘A�����u���l�ŁA�������̑������ړ����ϒl �@�@�@�@�������Ă���B�܂��A�����̋L�^��30m/s�A90m/s �@�@�@�@�����W�̎����؊����ł���A�����������Ȃ���20�� �@�@�@�@��17������21����2���܂ł�90m/s�����W�ƂȂ��Ă���B�j
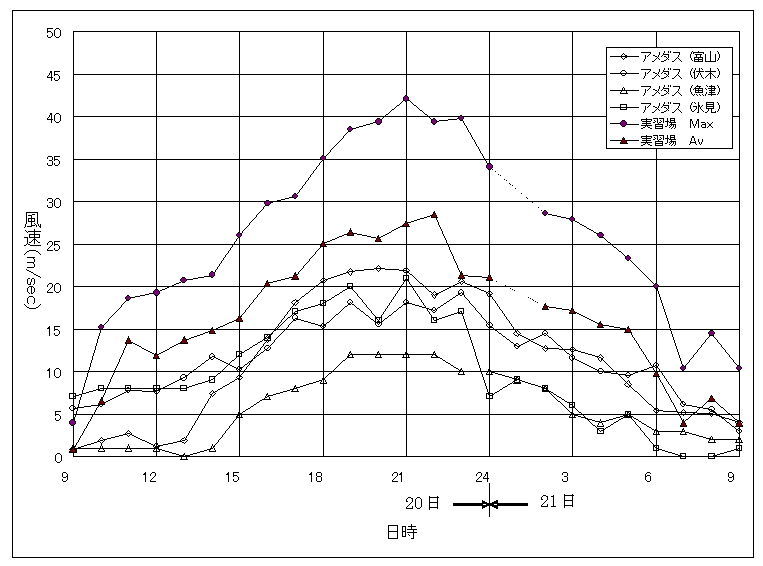
�}3.3�@�}3.1�̊e�ϑ��_�ɂ����镗����10/20��9������10/21��
9���ɂ�����ω�
(�A���_�X�f�[�^�͋C�ے�HP[1]��蔲��)
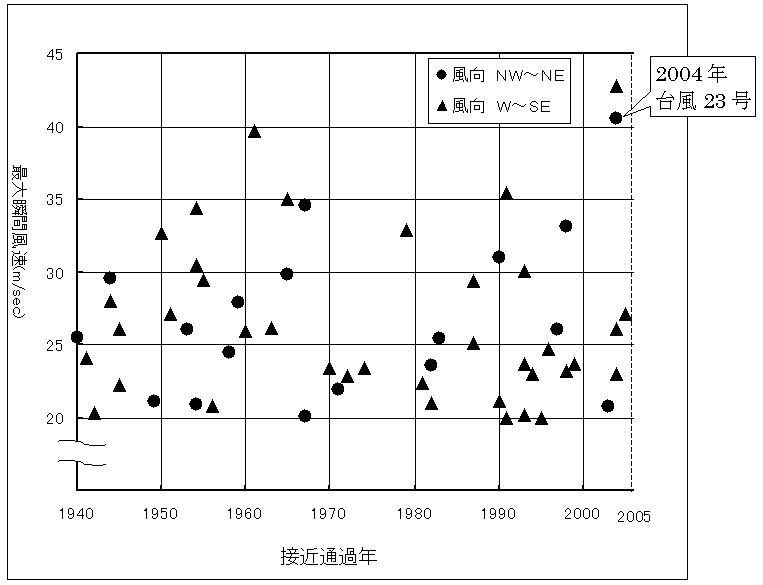
�}3.4�@�x�R���P�������ߋ��̑䕗�f�[�^�ɂ�����ő�u�ԕ����
�����̕��z
(�x�R�n���C�ۑ�f�[�^[3]���ő�u�ԕ���20m/s�ȏ��)
�@���ؕx�R�`���݈�ɂ����ẮA20���̂����悻18������21���̂����悻
0���܂ŁA������N����NNE�ň��ł���A���ϕ�������20�`25m/s�̕�����
���������̂ł���B�����āA�ő�u�ԕ����ł͕x�R�n���C�ۑ��42.7m/s�A
�x�R���D���K���42.1m/s�i20��20�����j�ł������B�C���ۂ̋L�^�ɂ���
�Ă�20����21�����ɑD�̑����60m/s���ϑ������Ƃ���B���̎��_�ł͊C��
�ۂ́A�܂����d�����ł��藤�݂���1�������x�̏��ɂ����Ǝv����B
������N����NNE�̕����ł������Ƃ���Ǝ��͂ɎՂ���̂͊F���̏Ȃ�
�ŁA����̃|�C���g��苭�����������Ă������Ƃ͏[���ɂ��肦��B����
�Ō���㏤�D�̑D���ł���A���{�D���������߂�ꂽ�쓇�T�����A
���a34�N�ɖ��É��`�O�ňɐ��p�䕗��𔑂����ۂ̋L�^[4],[5]���L�����
����̂ŁA���̊֘A�������Љ���Ē����B���a34�N9���Ɏ�ɓ��C�n���
�傫�Ȕ�Q�������炵���ɐ��p�䕗�͗���ɂ�����ő�u�ԕ����̊ϑ��́A
���É��ɂ�����45.7m/s�A�ɗnjɂ�����55.3m/s�ł�����[1]�B���̎���
�쓇�����D�����߂��㏤�D�́u�߂�ڂ��ہv�͋����ɑς��ꂸ��
�d�����A5������������ė��݂���2�C���̒n�_�Ɏ������B���̎��͖{��
�Ȃ���ʂ��鐅�[�ł��������A�C���痤�����ւ̕��Q�̐����ƁA����
����̖����̌��ʂ��獂����ԂƂȂ��Ă��āA���ʂ̓�͓��ꂽ�B�����āA
���̎��̕����s�[�N���ɂ͍ő�u�ԕ���50m/s�ȏ���펞�Ɋϑ�����悤
�ɂȂ��Ă���B�����������Ƃ���A����̑䕗23���ɂ����āA����ϑ���
�ő��42m/s�ŁA�C��ł͖�60m/s�͏[���ɂ��肠����ł���A�܂���
�ꂪ�펯�ł���Ƃ��v����B
�x�R���D�����C�m��ɍݐЂ���C�Z�֘A�҂ŁA���̕x�R��30�`40�N���Z
���镡���҂̈ӌ��Ƃ��āA������̕����������䕗�͊o���������Ƃ���
�ӌ��ł������B�����ŁA�}3.4�͕x�R�n���C�ۑ�HP[3]�Œ��Ă���A
�x�R���P�������ߋ��̑䕗�f�[�^�̈ꗗ���ő�u�ԕ�����������܂Ƃ�
�����̂ł���B�����ł̊ϑ���1940�N�i���a15�N�j���J�n����Ă���B
���������ƍő�u�ԕ�����35m/s���z������͔̂��ɋH�ł���A����
������W�`SE�ł���B������A����̑䕗�������ƕ����̗��ʂ̏�������
���āA�x�R�n���ł͔��ɓ��قȏł��������Ƃ�������B
�@�����������n�߂�ƕ��ɂ�鉞�͂ƊC�ʂɂ�����\�ʒ��͂ɂ��C��
�̔g�����������A���ꂪ�u�����g�v�ƂȂ�B�����āA�������オ�肻��
���͂��傫���Ȃ�ƁA����ɂ��ړ������C���̏d�͂Ƃɂ��g������
�����A���ꂪ�u���Q�v�ƂȂ�B�����āA�������ċN�����g�����C����}
���Ƃ��ĉ����ɓ`�����Ă����̂��u���˂�v�ł���B���̕��Q�����B��
�邽�߂ɂ́A���̉��͂������镗�̐������ԂƐ����������K�v�ł�
��B�Ⴆ�A����15m/s�̕�����肵�Ă���ꍇ�A�������Ԃ���20���ԁA
������������500km�ɒB����Ɣg���͖�5m�܂Ő�������[10]�B�\�E
�q�厁�̒����ł́A����܂őD�����e��m�ő��肳�ꂽ�����̔g����
������ƁA��ʂɔg��6m���z����p�x��10�`15���ɉ߂��Ȃ��Ƃ���B���A
���ɂ͔g��13�`15m�Ƃ����M�����ׂ������邪�A������͂邩�ɍ�
���g���`�������̂͂܂�ł���Ƃ���Ă���B����́A���͖�������
�͋����Ȃ炸�A�܂���������Ɏ��ԓI�A�ꏊ�I�Ɉ��ł͖����A����
���ԂƐ��������̌��E�����邽�߂ł���[7]�B
�M�҂�x�R���D����̋����́A����������w�����K���̂��߂Ɏ��K�D��
�x�R�p�̊C��ɏo��@������B�����ŏ�Ɋ����Ă��鎖�́A�k����
�k�����̕��̏ꍇ�A���������́A����̕��̏ꍇ�ɔ�ׂāA���Q��
���B�͊m���ɑ傫�����̂ł���B�܂������k����k�����̕�������
����1�����x��������́A�k���̂��˂肪�����ȍ~�ɏ�ɑ��݂���
���̂ł���B�������������Ƃ��ẮA�x�R�p���k�����ɑ傫���O�C��
������{�C�ɊJ���Ă��邱�Ƃ����邪�A���̘p���̊C��n�`�ɋN������
�Ƃ��������B�}3.5�ɓ��{���݂̒������Ɉʒu����x�R�p�̔z�u
�����͂̊C��n�`�Ƌ��Ɏ����B[11]���̕x�R�p�͖k���O�C����q����
���[����1,000������C��J�����߂��܂Ŗ��ڂ���\���ƂȂ���
����B���������n�`�ɋN�����āA�u�����g�v���N�艈�݈�ɍЊQ��
�^����ꍇ�������B�����̊T�v�������Ɏ����B
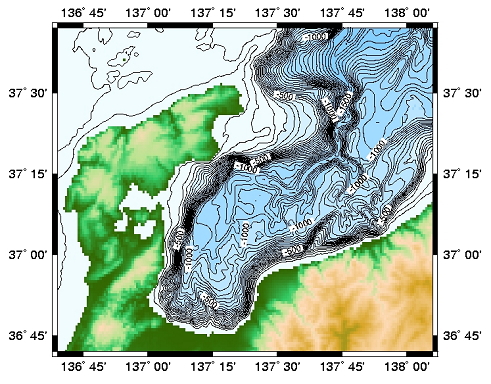
�}3.5�@�x�R�p�̊C��n�`[8]
�x�R�p�͐}3.5�Ɏ����悤�ɁA�k����������̔g�Q���N�����₷���`��� ����A���ɖk�C���������ł̕��Q�����Ƃ��钷�����̂��˂肪�A��z�g�Q�� ���ĐN������ꍇ�������B�����������ŁA�x�R�p�ɂ͌Â����u�����g�v �Ə̂�����ٔg�Q���ώ@����A�D���≈�݈�̌��z�E�y�ؐݔ���l���ɑ傫 �Ȕ�Q��^���Ă���[9]�B���̌��ۂ͕x�R�p���牓�����ꂽ�k�C�������ɔ� �B������C��������ꍇ�ɔ������₷�����̂ł���B �@����͕x�R�p���L�̑傫�Ȕg�������������˂�ł���A�p���̋������� �܂�����˔@�Ƃ��ė��P���邱�Ƃ�����B�}3.6�ɔ����ߒ��������B���� �����́A��ɖk�C�������C��Ŕ����������Q���A���˂�Ƃ��ĕx�R�p�ɓ`�� ���Ă��邱�Ƃɂ���B�k�C�����邢�͂��̓����C��ɔ��B������C��������A �k�C�������C��Ŗk���̋��������������ƁA���̊C��ō��g���������A�� �̍��g����쐼�ɓ`�����Ă����B�������ĕx�R�p�܂œ`�����Ă����g�́A �}3.5�Ɏ������x�R�p�̐��[���z�̓����ɂ��A�G�l���M�[����������邱�� �Ȃ����݂ɒB����B���ʂƂ��āA�����É��ł��鎞�ɁA�˔@�Ƃ��ĉ��ݕ��� ��g���P�����ƂɂȂ�B2004�N��12��6���ɂ́A�x�R�p�ɂ͒�������[���ɂ� ���āA���̌����Ȋ����g���P�������B���̓��̒�9���̓V�C�}��}3.7�� ����[13]�B���̓��͖k�C�������C��Ŕ��B������C���������ł���A ����ɂ��x�R�p�ł͐����ɒB���鉈�ݔg�����ϑ�����Ă���B���̊��� ��g�������ɔ������邽�߂ɂ́A�}3.7�Ɏ������C���z�u���P�`�Q�����x�ȏ� �ɒ�����Ă���K�v������B�������Ėk�C�������C��Ŕ��B�������Q���A �x�R�p�ɁA�����Ŗ�11�`12�b�A�g���Ŗ�100�`120m�̂��˂�Ƃ��ē`�����Ă� �����ɁA���ݕ��Ō����Ȋ����g���������₷���B�܂��A�����x�R�p�̉� �݂ł��A���̉e���������Ȓn��ƁA�����łȂ��n��Ƃ����݂���B�������� ���ۂ��N����̂́A�}3.6�Ŏ������悤�ȕx�R�p�̕��G�ȊC��n�`�ɁA���L�� �������������g���`������ɓ�����A���ʂȑ������t�B���^�[���ʂ��y�� ���Ă���Ǝv����B
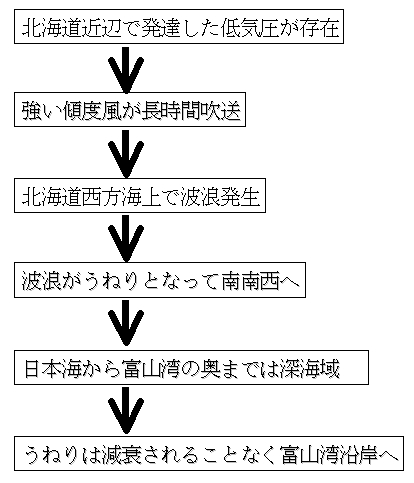
�}3.6�@�����g�̔����ߒ�
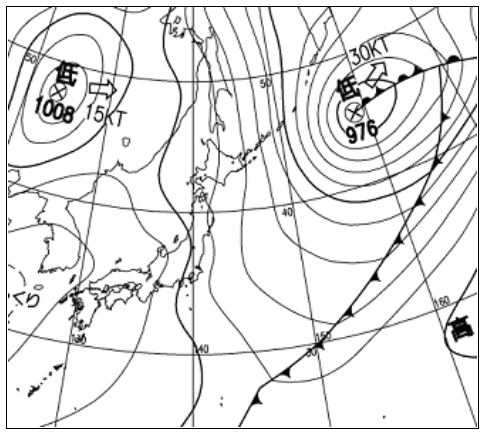
�}3.7�@�����g�������̓V�C�}[10]
(2004�N12��6��9��)
�@�x�R�p�ɂ����Ă͖k�����畗�Q�₤�˂肪�N������ۂɂ́A��ɑ����ꏭ��
���ꉈ�ݕ��Ŕg�������傷�錻�ۂ��������Ă���ƌ�����B����͕x�R���D��
��ʼn��ݕ���p�ɂɍq�C����E���̋��ʂ��������ł���B�����Ő}3.8��B�͊C
���ۂ������̕d�������n�_�������Ă���B�x�R���h�g�瓔�����1,900m�̐�
�[��17m�̒n�_�ł���B�����́A���C���ł����ɏo��ΐ��[��50�`100���ɂȂ�
�Ă��܂��n�_�ł���B���������ꏊ�ɂ����d�n��ݒ�ł��Ȃ��̂��A���̕x�R
�p�̊C��n�`�ɋN������A����`�ł��镚�ؕx�R�`�̌���ł���B
�@�}3.8���Ɏ������@�A�A�̓_���ɂ�����C��n�`�f�ʂ�}3.9�Ɏ����B������
�����悤�ɉ��Ɍ������ĊC��n�`���}�s�ɗ�������ł��邱�Ƃ�������B���
�I�ȗ��_�ɂ��ƁA�����痈��[�C�g���A���[�����̔g���̖�1/2��菬������
��Ƃ킸���Ɍ��邪�A��1/10�̏��܂ŗ���Ɣg���������n�߁A��1/20�ɂȂ��
�}���ɑ����Ƃ���Ă���[11]�B�x�R�p�̋}�s�ȊC��n�`�ł́A�g���̔��B����
�ݕ��ł�͂�}�s�ɍs���邱�Ƃ��z���ł���B
�@���y��ʏȖk���n�������Ǖ��ؕx�R�`�p�������ł͕x�R�`�ƕ��؍`�̉��̊C
��ɔg�Q�v��ݒu���āA�L�`�g���A�L�`�g�����A�g�����̏펞�ϑ����s���A����
�����قڃ��A���^�C���Ƀz�[���y�[�W[12]�Ɍ��J���Ă���B�}3.8��A�ɕx�R
�`���̊ϑ��_�������B��������300m�A���[��19m�n�_�ł���B���̔g�Q�v�͊C��
�ɐݒu����A���̓Z���T�[�̕ϓ�����g�����A����ɒ����g�̃}���`�r�[����
�Ǝ˂��A���̔��˔g�̃h�b�v���[�V�t�g����g���Ɣg���������߂Ă���B����
�āA�������A�����̌v���l���Z�o���Ă���B�}3.10�́A���ؕx�R�`�p������
�����ꂽ�f�[�^�ɂ��A10/20��10������10/21��10���܂ł́A���̌v���l
�̕ω����O���t���������̂ł���B������g�����͏�ɖk����k���ł�������
�Ƃ�������B�����ăs�[�N���ɂ�6�����z����L�`�g���ł��������Ƃ�������B
�܂���ۂɂ́A���̔{���x��10������g�������݂��Ă����Ǝv����B����
�C���ۂ����d���������ԑтɂ����ẮA�O�m�ł��܂�Ȕg�Q�����݂��Ă����킯
�ł���B
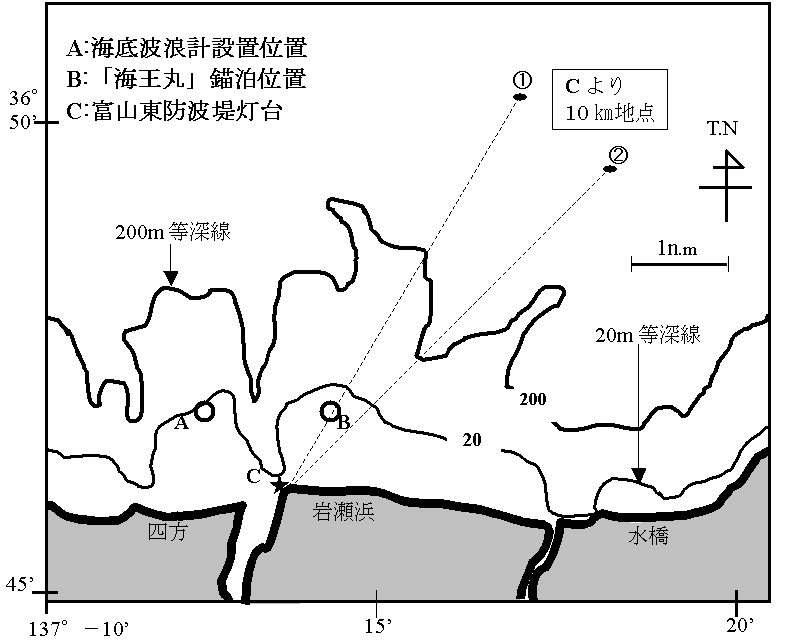
�}3.8�@�u�C���ہv�d���ʒu���͂̓��[���}
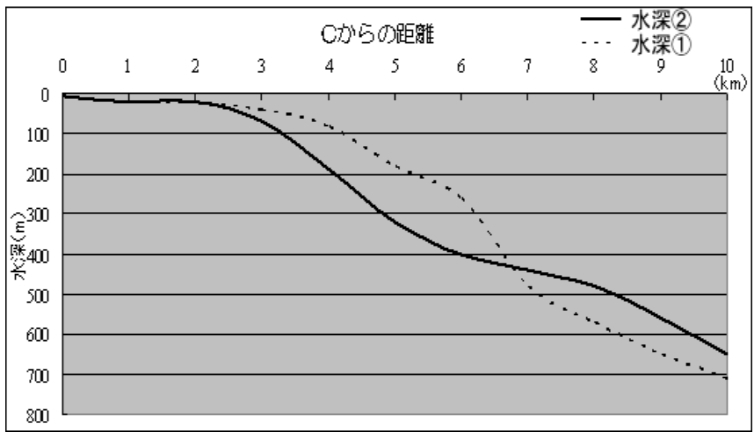
�}3.9�@�}3.8�̓_���@�A�A�ɂ����鐅�[�ω�
�i�x�R���h�g�瓔��C����_�Ƃ���B�j
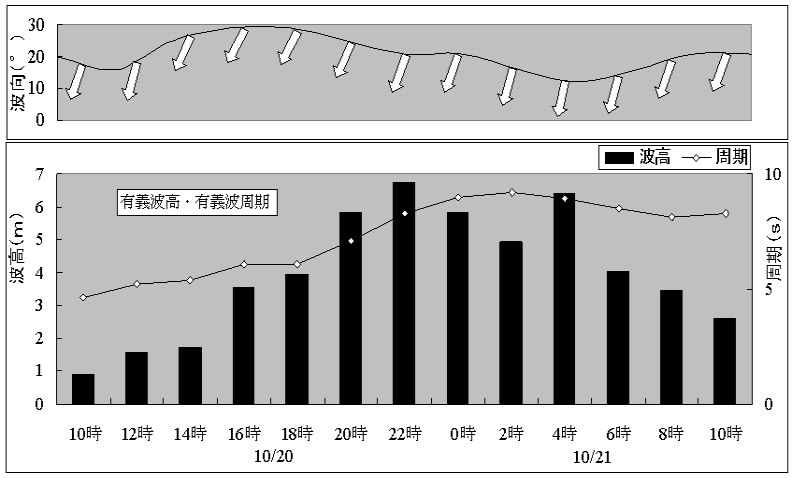
�}3.10�@�C��ݒu�g�Q�v(�}3.8��A)�ɂ�����10/20 10���`10/21 10���� �@�@�@�@�L�`�g���E�L�`�g�����E�g���̕ω� �@�@�@�@(���ؕx�R�`�p�������f�[�^[12]�ɂ��)
�@���A�C�ۊC�ۂւ̍l�@�̍Ō�Ƃ��āA�����̕ω��ɂ��ċL���Ă����B
�}3.11�ɂ�10/20��9������10/21��9���ɂ�����������ʂƒ��ʕ�(����
���ʁ|�\���V������)�������Ă���B�m1�n���X�A���{�C�ɂ���������
���ʕω��͏��Ȃ��A�x�R�p�ɂ����Ă���10cm�ȉ��̏ꍇ���w�ǂł���B
���ۂɂ����Ɏ����������ʂ̕ω��͖�40cm�ł���B�܂��A��������ƁA
���傤�Ǒ䕗�̍Őڋߎ��ɕ�����20cm�ƃs�[�N�ɂȂ��Ă���B�����
�䕗�̒��S�̒ሳ���ɂ��A�C���̋z���グ���ʂƔg�ɂ�鐁����
�����������̂Ǝv����B�������A�����͊C���ۂ̑��d�y�э��ʂɑ傫��
�������y�ڂ������̂ł͖����ƌ�����B
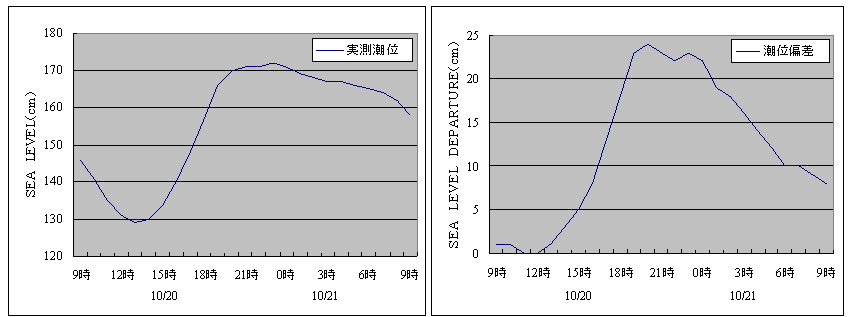
�}3.11�@�x�R�`�ɂ�����10/20 9���`10/21 9���̒����ω�
�i�C�ے�HP�m1�n�f�[�^�ɂ��j
�@���̑䕗�ɂ��C�ۊC�ۂɂ��ẮA�C�ۊw��C�m�����w�̌��n����́A ��藝�_�I�Ȍ������ł���ł��낤���A�܂�����ɂ�薾�m�Ȓm�������� ���鏊�ł���B�n���̊C�Z�W�҂̌����Ƃ��ẮA���̑䕗�ł͕x�R�ł� �܂�Ɍ�����k���̖\�������ؕx�R�`�ߕӂɒ����Ԃɐ������Ƃ�����B �܂��A���̕����A���̉��ݕ��̊C��n�`�̉e������A��͂�܂�Ɍ���� ���Ȕg�Q���������Ǝv����B �@���A���̑䕗�̖҈Ђɂ��A�����s�̕��ؖ��t�ӓ��ŁA�Q�O����A�ݕ� �W�����̃��V�A�D�Ђ̉q�D�A���g�j�[�i�l�W�_�m�o���i�S�Q�T�S���g���j �����g�ŊݕǂɏՓ˂��A�Z�����ĉ��]�����C��������B����Ə�q�� �X�O�l�͔��Ă��Ė����������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF��t�@���j
�@���_�I�ɂ́A�䕗�����߂����d���n�Ƃ��Ă͕s�K���ł������B
�x�R�p�́A�\�o�����ɎՕ�����Ėk���̋G�ߕ���h�����Ƃ��o���邪�A
�k����������̕��g�ɑ��ẮA�S�����h���ł���A�p�̐��[���[���A
���݂ɂ���߂ċ߂��ꏊ�ŁA���݂��ɂ��ĕd�����邱�ƂɂȂ�B
�����̂��Ƃ���A�����̑D���́A�̂���䕗�┭�B������C�����
������ꏊ�Ƃ��ĕs�K���Ƃ��Ă���B���ؐ���l��z�O������
�u�x�R�p�ɂ�����������d������A�䕗�Q�R���ɂ���ĕx�R�p�͈�
�ԏ����̈����k���̕����������Ƃ����O�ɗ\������Ă����B��ʑD��
����������������ł��낤���D�̊C���ۂ����ԓI�ɗ]�T������
�Ȃ���A�ǂ����āA���S�ȊC��ɔ����ɕd���ő䕗�����߂���
���Ƃ����̂�������܂���v[13]�Ƃ����A�܂��A���{�D������s�씎
�N�햱�����́u�䕗�Q�R���ڋ߂ɂ��x�R�p�̕����͖k�`�k�k���ŁA
�p���Ɍ������Đ������ł��邱�Ƃ͗e�Ղɗ\���ł����Ǝv���܂��B��
�����A���͂̋����䕗���ڋ߂��Ă�����ŁA���ォ��̋������P
�}�C���ɖ����Ȃ��C��ɕd������̂͂�����ƍl�����܂���B�����@
����̏ꍇ�͗����牫�Ɍ������Đ������ł͂Ȃ��t�̏ꍇ�ł�����v
�Ƃ���[13]�B
�@�c���͂ɂ��ẮA�����X�N�A�V���A�x�R3�ӏ��A�����̎��D������
�ʁi�ψ����F�R��S��A[14]�j�ɂ��A���̕t�߂ŗǂ��Ƃ���镚��
�̂W����̔c���͂��ϑ����A�ϑ������T�̒n�_�̒��ő�R�ʂł������B
�ǂ��Ƃ͌����Ȃ����ʂł͂��邪�A���{�C����v�`�p�ł͊T�˗ǂ��ƌ�
���鏊�����Ȃ����Ƃ𑊑ΓI�ɍl����Ɓu�ǂ��Ƃ͌����Ȃ��������Ƃ�
�����Ȃ��v���x�ł���B�ȉ��ɁA���̕d�n�̔𔑒n�Ƃ��Ă̈�ʓI�ȕ]
���𗝉����邽�߂ɁA���{�C�C��h�~����s�����A�������ʁi�ψ���
�F�R���S��A[14][15]�j�j�ɂ�����A���P�[�g�������ʂ̈ꕔ�������B
�q�C�P�����́A�����̓��{�C�C��h�~����̒������ʂ���肵�Ă���
�������B�܂��A���̂悤�Ȓ������s��ꂽ���Ƃ����m���Ă��Ȃ������B
����e�n�̊C��h�~����邢�͌�����ɑ��A���������s���A����
���ʕ������o���ꂽ�ꍇ�ɂ͎�������悤�A�����ɂ��˗���
���B
�i�P�j�����Ώ�
�@�����[�����̉�
����8�N9���`����9�N2���A�����ĕ���12�N�V���`12���ɓ��{�C�����C��
��v�`�ɂ�����d���Ɋւ��钲���[���������{�����B�����D������
�}4.1�Ɏ����Ƃ���ł���A�㗝�X�̋��͂ĂU�Q�R��(���A�O���D
214��)����̉��B�����āA���ؕx�R�`�ł͂P�T�X�ǁi�Q�U���j
����̉��B
�A�����D���̑��g����
�����D���̑��g�����͐}4.2�Ɏ����Ƃ���ł���A���̖w�ǂ�6000
�g���ȉ��ł���A���̂����A1000�`6000�g���������i�T�S���j���߂��B
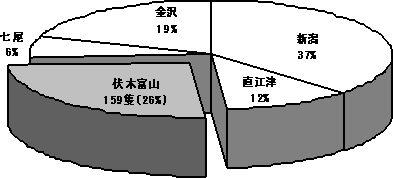
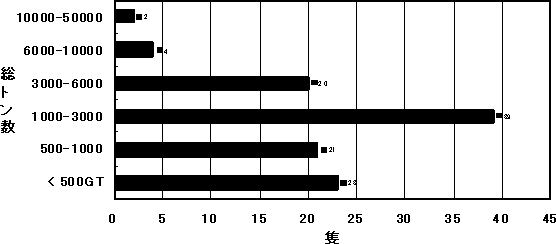
�i�Q�j���ؕx�R�`�̕d�n�ɑ���D���B�̔F�� �@���ؕx�R�`�̕d�n�̔F���ɂ��ẮA�}4.3�Ɏ����Ƃ���A �u��ɕs���i�V���j�v�A�u�G�߂ɂ��s���i�T�X���j�v�A �u�o���邾���d���������i�P�S���j�v�A�����ĂW�O�����A �u�d�n�Ƃ��ēK���łȂ��v�Ƃ����]���������B
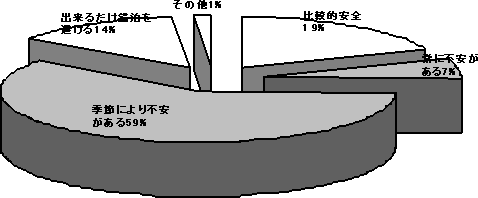
�i�R�j�s���̓��e �@�u�G�߂ɂ��s���v�A�u��ɕs���v�Ɖ����D���ɂ��̕s������ �Ƃ���A�}4.4�Ɏ����Ƃ���A�u�n���I�������畗�Q���Օ��ł��Ȃ��v�A �u�g�Q�̉e�����傫���v�A�u�d�n�������v��56%���߂��B
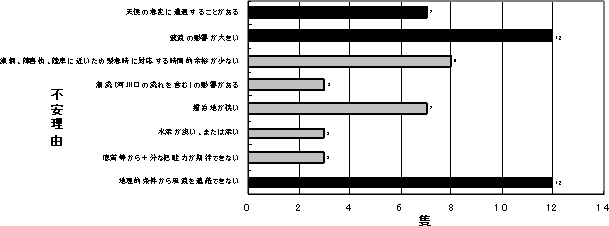
�i�S�j�u�o���邾���d���������v�Ɖ����D���̑Ώ����@ �u�o���邾���A�d���������v�Ɖ����D���̑Ώ����@�́A�}4.5�Ɏ��� �Ƃ���A�O�����Ē��ݎ��Ԃ��m�F�̂����A���Ԓ��������ē��`���݂���� �������Ƃł������B
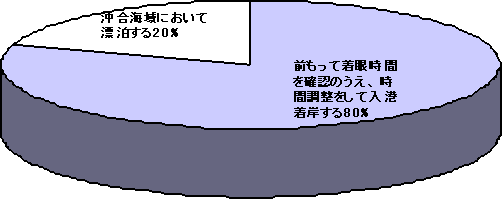
�i�T�j�u�𔑒n�Ƃ��ēK���ł��������v�Ɋւ���A���P�[�g�Ɋ�ꂽ�ӌ� �@���ؕx�R�`�̕d���n�ɂ��Ă̋C�ہE�C�ۂɊւ��ӌ��E�v�]�����R�L�q�ŕ� �����Ƃ���A�C�ہE�C�ۂɊւ��ӌ��͂��̂Ƃ���ł������B �@�~���A�k���̕����������͑�ϕs���ł���B�P�~�J����ς�ł��邪�A�o�[�X �@���Ă����璅�V���Ă����������S�ł���B �A�~�͕d���������Ȃ��B�d�����Ă��Ă����r�V�ɂȂ邩������Ȃ��B �B�O�m�ɖʂ��Ă���A�ǂ��Ȃ��B�Y�����Ē��݂�҂��������ǂ��B �C���������ł͂Ȃ��g�����傫���W����B�O�C�ɖʂ��Ă��邽�߁A�d���ɂ� �@�Ă͂��Ȃ�l����������B �D�G�ߕ��̋����Ƃ��͕d���͂Ȃ�ׂ������������悢�B �E�����g�������A�����ɂ��D������������₷���A�~�G�ł��˂�̑傫���� �@���͑��d���₷���̂Œ��ӂ�v���B �F�k���A�k����̂��˂�Ɏア
�@�ŋ߂R�O�N�ȓ��ɁA�~���̋G�ߕ��A��ʒ�C���ɂ���ĂQ���̑��d�C�� ���������B��������k���̕��g�ɂ��e�����Ă���B�������A�䕗�� ��鑖�d�C��͌�������Ȃ��B�䕗���̍r�V���ɕ��ؕx�R�`�ɂ����Ĕ𔑂� �Ă����D�����Ȃ��������炾�ƍl������B �@�ȉ��ɁA�Q���̊C��R�����ٌ����C��R���ٌ��^����v��B
�i�P�j���������F���a62�i1987�j12��2���ߑO5��15����
�i�Q�j�����ʒu�F���،��u�d�n�A(36��-48.1N,137��-04.2E�j
�@�@�@���d��̈ʒu�F���ؓіh�g�瓔�䂩��312��185��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@(36��-47.8N�C137-04.2E�j
�i�R�j�C��D���@�F�@�@�D��F�ݕ��D
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@���ЁF���{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@���g�����F696�f�s
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�@��g�����E���ЁF���{�l�@7�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�ω�ԁF�����i�Ƃ����낱���j�@2000�g��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g�p�d�y�ѕd���̐ߐ��F�E���d5�߁A���[9���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ꮏ�F��
�i�S�j���̌����@�F�d�n�̑I�肪�s�K�A�┑�����̑ӂ�A�r�V�����s�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�����́A�C��\���w�\���ɂ�����d�n�̑I��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���s�K�ŁA���g�̉e���������镚�؏��R�`�O�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɕd���������肩�A�����L�o�y�s�\���̂܂ܒ┑��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����z�u���Ȃ��������߁A�g�Q�̑����ɑΏ��ł����A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���d�������ƂɈ����Ĕ����������̂ł���B
�i�T�j���̊T�v�@�F����2�C000�g����ς݁A11��28��2240���������u�z�u
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`���o�`�����ؕx�R�`�i���؋�j�Ɍ��������B12��1��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@2000���`�O���A���،��u�d�n�i���[9���Ꮏ���j�ɉE��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��5�߂ŕd�������B������A�D����1�l��1���Ԗ��Ɍ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������{���Ă����B2��0500�̌����̍ہA���d���Ă�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��̂ɋC�t�������Ɏ�@���N���������Ԃɍ��킸�A0540
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ؓіh�g�瓔�䂩��q312�r185���ɏ�g�����B
�i�U�j���d�������F�@�@�V�C�F�݂���@�@�A�@�����F�k���@�����F6���^s
�@�@�@�̋C�ۊC�ہ@�B�@�g�Q�F�k���@4�@�C�@���˂�F�k���@4�@
�@�@�@�@�@�@�@�D�@�����F3�����@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�ő�u�ԕ����F18�D3��/s�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F�k�k���@2��02��30��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�@�ő啗���@�F7�D6��/s�@�����F�k�k���@2��02��40��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�@�x��E���ӕ�F�g�Q�x��A�������ӕ�
�i�V�j�C�ۊT���@�F1���͓��{�C�Ɗ֓�����2�̒�C�������B���Ȃ���
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k���ɐi�݁A���̌㎟��ɓ~�^�����܂�A2�����~�^��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���z�u���������B1���������畗��J�����܂�A��ɂ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�J����ɕς�����B
�i�W�j���Q�@�@�@�F�ǂɑ����A�D��ɔj��
�i�P�j���������@�F�������N�i1989�j3��8��01��180����
�i�Q�j�d���ʒu�@�F�x�R���u�d�n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x�R�іh�g�瓔�䂩��030��1180��
�@�@�@�@�i36��-46.3�m�C137��-14.3�d�j
�@ ���d��̈ʒu�F�����䂩��055���@230��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i36��-45.8�m�C137��-14.0�d�j
�i�R�j�C��D���@�F�@�@�D��F�^���J�[
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�@���ЁF���{
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�B�@���g�����F999�f�s�@�S���F76��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�@��g�����E���ЁF���{10�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�ω�ԁF��D
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�@�g�p�d�y�ѕd���̊�F�E���d5�߁A���[13���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ꎿ�@��
�i�S�j���̌����@�F�C�ۊC�ۂɑ���z���s�\���A�┑�����̑ӂ�
�@�{����g�́A��ԁA�k���ɊJ�����Ă��镚�؏��R�`�ɕd������ɂ���
��A�C�ۏ��̓��肪�s�\���̂܂܁A��d�����Ȃǂ̑��d�ɔ�����[�u
���Ƃ邱�ƂȂ��d�����A�C���̒J�̒ʉ߂Ɠ~�^�̋C���z�u�ɔ���������
���k���̕��Q���A�h�g��Ɍ����đ��d�������ƂɈ����Ĕ���������
�̂ł���B
�i�T�j���̊T�v�@�F3��7��1730���]�Í`���o�`�A����2230�����ؕx�R�`
�i�x�R��j�x�R���h�g�瓔�䂩��030����1180���t�߂ɉE����5�߂ŕd��
�����B�d���n�̐��[11���ꎿ���ł���A�Y�D�͋�D�ŋi���D���1.15���A
�D����3.2���ł������B�D���͓K�ȋC�ۏ��̓����ӂ�r�V��\�z�o
�����A��d�����𗧂Ă��ɏA�Q�����B8��0118���h�X���Ƃ����Ռ��őS�_
��ыN�������A���ɉE�����ݑ��Ɍ������g�u���b�N�ɏ�g���Ă����B
�i�U�j���d�������́F�@�@�V�C�F�܂�@�A�@�����F�k�k���A�����F14m/s
�@�@�@�C�ۊC�ۏ@�B�g�Q�F�k�k���@4�@�C�@���˂�F�k�k���@3�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�����F18����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�u�ԍő啗���F20.3m/s�@�����F�k���@8��02��10��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�ő啗���@�@�F12.8m/s�@�����F�k���@8��02��20��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�x��E���ӕ�F�����E�g�Q���ӕ�
�i�V�j�C�ۊT���@�F7�`8���ɂ����ċ����~�^�̋C���z�u�ł������B
�i�W�j���Q�@�@�@�F�E�����O�y�ёD��ɔj���������A��g���R�l��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���S�A�Q�l�������@
�@���ؐ���l�R���������́A�Q�O�������̓��`��Ƃ��I���O�X�����Ɏ��� ���ɋA���ĂقǂȂ��C���ۂ��x�R�p�ɓ���A�x�R��̉����ɓ��d�������� ��m��B�䕗�̉e�����܂������Ă��Ȃ��������A���̐i�H����x�R�n���� �����̑�r��ɂȂ邱�Ƃ��\�z����Ă����B���݂̓��d�C�悪�����ɑς� ��̂ɕs�����ł��邱�Ƃ��n�m���Ă����R���p�C���b�g�́u�C���ۂɓ`�� �Ȃ���v�ƂO�X���R�O�����ɑ㗝�X�ɓd�b���āu�����p�ւ̔����S �ȊC��ɉ������悤�A�D���Ɋ��߂Ăق����v�Ɨv������[13]�B�������A �C���ۂ͓����Ȃ������B �O�q�̕d�����̎��D�����́A���d���A�d����L���d����������ԂŁA�� �i�G���W���������ĕd�𑖕d����܂ň�������A���̒��͂ɂ���Ĕ�r�� ��������̂ł������B�����`�ł́A�x�R��̂S�����x�̕d�����͂����ϑ� �ł����A����߂Ĉ������ʂ��o���B���Ȃ킿�A�d�̒܂��������݂ɂ����A �d�����v���ɂ�����Ԃł������B�܂��A�k������̕��A���˂�́A�\�o�� �ɂ��Ղ���B���������̌ߌ�ł́A���������Ȃ�A�������A������� �����̂œ��Ă��Ȃ��l�ɂ͓���ɂ����B �@���̂Q�_���l�����킹��ƁA�����`�ɌߑO���V�t�g���邱�Ƃ��o����A �d�����������đ��d�����Ƃ��Ă��A�K�ɋ@�ւ��g�p�������̎��̂� �N���Ȃ������ł��낤�B
�@�O�q�̃A���P�[�g�����ɂ����āA�}4.6�Ɏ����悤�ɁA���ؕx�R�`�ɒ�
������D�̈Ӑ}����𔑒n�́A���n�����ӂS�U���A�ѓc�p�Q�S���A�����p
�P�S���ł���A���̗��R�́A�}4.7�Ɏ����悤�Ɂu���ɓK���ȏꏊ���Ȃ��v
���Q�X���ƂȂ��Ă���B�ѓc�p�͈ꕔ�̋����C��������āA�k������̕��A
���˂�ɂ͎ア�̂ŁA�䕗�Q�R���̏ꍇ�́A���n�����ӂ����ǂ��𔑒n��
�Ȃ��B�]���āA�x�R��ɗ���O�ɁA���S���Ƃ��A���n���̓��e�ɔ�
�đ䕗�̒ʉ߂�҂̂��x�X�g�������B���̂Ƃ��A�R�ǂ̑�^�t�F���[��
���n�̓��e�ɔ��Ă����B
�@�x�R��ɕd����������l����ƁA����A���˂肪�傫���Ȃ�̂�\�����A
�����ɂƂǂ܂炸�A�ߑO���Ɏ����Ɍ����ւ悩�����B����ɁA�x�R���
�A���J�[���A���Ԃ��o�߂��Ă��܂����ꍇ���l����ƁA�ߑO���A�`���̂�
�˂�̉e���̏o���邾�����Ȃ��ݕǂɃV�t�g����悩�����B���̏ꍇ�́A
�`���ɐN�����邤�˂�ɑΉ����邽�߂ɁA�A���J�[�����A�W�����
�Ƃ�A�^�O�{�[�g���g�p����B���ɁA���ؕx�R�`�A�V���`�ł́A�d���D��
�Ȃ��A�V����A�V���`�̊ݕnjW���D�ɑ傫�Ȕ�Q�͖��������B
���ꂪ�o���Ȃ���A���߂ɃA���J�[��g���A�p���Ɍ����ĉ��ɏo�āA
�����イ����悩�����B
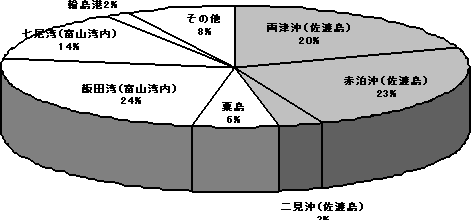
�i�R�j�r�V�𔑒n�̑I�藝�R �𔑒n�I��̗��R�͐}�@�Ɏ����Ƃ���ł������B
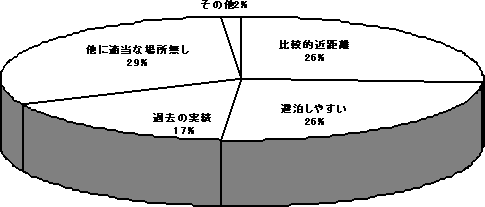
�i�S�j�A���P�[�g�Ɋ�ꂽ�ӌ�
�@�~��̓��{�C�ł̔��`����ΓI�ɏ��Ȃ��B�l�H�I�ɂł��ݔ�������
�@���S�ƂȂ�B
�A�r�V�̏ꍇ�A�K���������������u���Ƃ������Ƃ������ɖh�g����d��
�@�����肢�����B
�@�M�҂́A�D���B�̂����̈ӌ��͒ɂ��قǗ����ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j
�@��ʓI���H���Ƃ��āA�D������ł�����ɂ���Ă���A���H���ɂ���
��𔑏��[16]�͂ǂ��ł����������������ʂ����ɏЉ��B
�x�R�p�́A�{�B����k���֓˂��o�����\�o������k�������ɍT���A�k����
���ɘp�����J������̘p�ł���B���̒n�`���G�ߕ��ɂ��k������̔g
�Q���Ւf���A���ɓ~�G�͑��̓��{�C���݂Ɣ�r���āA�g�����Ȃ������ȊC
��ƂȂ��Ă���B�Ƃ��낪�A���̕x�R�p�̒n�`�͖k������̔g�Q�ɑ���
�͋t�ɏ����������A�D���̔j����d�E���g���A�C�ݐZ�H���̍ЊQ����
�����Ă���B���N�P�Q���`�S�����ɁA��C�������{�C��ʉ߂��A���̌㕗
��g�����܂�A�C�ʂ��Â��ɂȂ������ɓ˔@�Ƃ��ĕx�R�p���݂ɉ����A
�ЊQ�������N���������g�͓��ɗL���ł���B�����āA�x�R�p�̂�����
�̓����͋}�[�Ȓn�`�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł���A���ɏ���ȓ��́A�}�[��
����C�ݐ�����P�`�Q�C�����ɂł�Ɛ��[100m�`200m�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�
����B���̂��߁A�d�n�͋�����[���d���n�߂�Ə��g����������邱��
������ł���B
�@�C��ۈ������H���ҏW�̖{�B�k���ݐ��H���ɂ́A�Q�y�[�W���̎��ʂ���
���āA�x�R�p�Ɋւ���q�C�E�┑�̎w���ē����L�ڂ���Ă���B�����āA
�x�R�p�Ɋւ��鎆�ʂ̖���p���Ċ����g�̊댯���ɂ��ċL�q��
����A
"�����g�́A�k�C�������C��Ŕ��������g�Q�����˂�ƂȂ��ĕx�R�p
�ɉ����A�x�R�p�̋}�[�Ȓn�`�̉e���ɂ�艈�߂��ŋ}�ɔg����
���A�ނ�l��~���Ɍ��������x�������S���铙�̍ЊQ�������N����������
������댯�Ȕg�ł���B"
���Ƃ��Љ��Ă���B�����g�́A�x�R�p���k������̔g�Q�Ɏキ�A
�k������傫�Ȕg�Q�����P����ꍇ�A���Ɋ댯�ł��邱�Ƃ����B�ɋ���
�Ă���̂ł���B�܂�A�x�R�p�͖k���̋G�ߕ��ɑ��Ă͈��S�ł��邪�A
�ړ�����C���̒ʉ߂ɂ��k������̔g�Q���N������ꍇ�͊댯�ł���A
���g�����ʎ��̂��x�X�������Ă���Ƃ������Ƃł���B�����g�́A
���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��x�R�p�ŗL�̔g�ł��邪�A�����Ɏ��Ɏ����x�R�p
�̓����ɂ��Ă��A���H���ɖ��L���Ă����ׂ��ł���Ǝv����B
(1)�}�[�Ȓn�`�ɂȂ��Ă���A�d�n�������B
(2)�~�G�ł���r�I�g�����Ȃ������ȊC��ƂȂ��Ă��邪�A�k������̔g
�@�@�Q�ɑ��Ă͊댯�ł���A���g�����ʎ��̓����������Ă���B
�i���ӁF�͍���i�j
�@���_�I�ɂ́A�q�C�P�����̈��S�Ǘ��̐��͕s�\���ł������B�@�h�r�l
�R�[�h�i���ۈ��S�Ǘ��R�[�h�A�C���^�[�i�V���i���E�Z�[�t�e�B�E�}�l
�[�W�����g�j�Ƃ́C�P�X�X�R�N�P�P���C�h�l�n����ɂ����č̑����ꂽ
���cA.741(18)�uInternational�@management�@Code�@for�@the�@Safe�@
Operation�@of�@Ship�@and�@for�@Pollution�@Prevention
(International�@Safety�@Management�FISM�@Code)�v�̂��Ƃł���B
�h�r�l�R�[�h�́C�P�X�W�V�N�i���a�U�Q�N�j�R���ɔ��������uHERALD�@
OF�@FREE�@ENTERPRISE�v���]�����́i�P�W�W�l���S�j���_�@�ɁC�p����
���S�ƂȂ��Đ��肳�ꂽ�D���Ǘ��̂��߂̋K���ł���B�@�h�l�n�́C�]
������ݔ��E�\���i�n�[�h�v���j�̊������Ă����B�������C�C�
�̂̌����́C�T�˂W�O�����u�l�I�v���v�ɂ����̂Ƃ����C�C���
�h�~�̂��߂ɂ́C�D���̈��S�^�q���m�ۂ���̐����\�z���邱�Ƃ��ł�
�d�v�ł��邱�Ƃ����������B���̂��߂ɂ͑D�������łȂ�����̊Ǘ���
����܂߂��S�ГI�Ȏ��g�݁C�����C���S�Ǘ��V�X�e���i�\�t�g�v���j
���K�v�ł���Ɣ��f����Ɏ���C�h�r�l�R�[�h�����肳�ꂽ�B�P�X�X�S�N
�i�����U�N�j�ɂh�l�n�ɂ����č̑����ꂽ�r�n�k�`�r���ɂ́C�V����
�u�D���̈��S�^�q�̊Ǘ��v����X�͂Ƃ��Ēlj�����C���̒��Ɂu��Ђ�
�h�r�l�R�[�h�̗v���������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��v�ƋK�肳��Ă�
��B���̃R�[�h�̍����@�߂Ƃ��āA�P�X�X�W�N�i�����P�O�N�j�P���P��
����u�D�����S�@�{�s�K���v�̑�Q�͂̂Q�Ɂu���S�Ǘ�������v���K��
����{�s�������B
�@�]���A�u��U�C�`�𗣂��Ɖ����N���邩������Ȃ��v�Ƃ����`���I
�ȍl��������Ǘ��́A�D���l�̐ӔC�ɂ��s���A�}�j���A���I�Ǘ�
�͕s�K���Ƃ���Ă����B�������A�h�r�l�R�[�h�́C�Ǘ��ӔC����Ђɂ�
�����B���̂��Ƃ́A�v���I�ȕω��ł������B�D��܂��͑D���̈��S�Ɋ�
���ĐӔC��L����ҁi��Ёj�Ɉ��S�Ǘ��̎��{���`���Â����̂ł���B
��̓I�ɂ́C��Ђɑ��āC���S�Ǘ��V�X�e���i�r�l�r�j�̍���E���{�C
����S���҂̑I�C�C���S�^�q�}�j���A���̍쐬�E�D���ւ̔����t���C��
�}���Ԃւ̏����E�Ή��葱���̊m���C�D���E�����̕ێ�葱���̊m����
�s�킹�����C�D���ɑ��đD���ɂ�������S�Ǘ����x�̈ʒu�t���C��
�ǒ��Ȃǂɂ����S�Ǘ��V�X�e���̐R���C��`�����{�̍s���R��
�i�o�r�b�j�Ȃǂɂ��C���̎�������S�ۂ��悤�Ƃ��Ă���B
�@�K�p�D���́C���ۍq�C�ɏ]������C���ׂĂ̗��q�D�C�������q�D�C��
�ۍq�C�ɏ]������T�O�O���g�����ȏ�́C���^���J�[�C�P�~�J���^���J
�[�C�K�X�^���D�C��ωݕ��D�C�����ݕ��D�C���̑��̉ݕ��D�C�ړ���
�C�ꎑ���@�탆�j�b�g�Ƃ���Ă���B���Ԃł́A�O�q�D�Ђ͂��Ƃ��A
�����̓��q�D�Ђ�����𗦐悵�Ď��{���Ă��邪�A�q�C�P�����̗��K�D
�́C���p�ɋ�����D���Ƃ��Ĉ��S�Ǘ�������̔����u���`����Ə�����
�Ă����B�q�C�P�����́A����I�Ɉ��S�Ǘ��V�X�e�����A����I�Ɉ��S��
���V�X�e�����E�^�p���J�n�������B
�@���̂悤�ȍ��ۓI�Ȑ����̂Ȃ��ŁA�q�C�P�����́A����r��ɂ���f
�l���R�̎��K����������D���Ă���ɂ�������炸�A���̐��x�ɏ�����
�����S�^�q�x���̎��{���s�\���ł������B���̂��߁A�C���ۂ���䕗��
�Q�R���̉e���Œ��݂������킹�ĕd�������|�̕��������Ƃ��A�n��
�̐��H�������肵�Ă���A�䕗�̓������������A�C���ۂ��ɂ߂Ċ�
���ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ�������ł������B����������炸�A�S�Ă�D
���ɔC�����܂܂ł������B�q�C�P�����ɁA�g�D�Ƃ��Ĉ��S�Ǘ��ɕs�\��
�ȕ��������������Ƃ��c�O�Ȃ���ۂ߂Ȃ��B�q�C�P�����ł́A���̌�A
�����ɊC���ێ��̌��������E�Ĕ��h�~���ψ���������A���Ɏ�����
�S��[17]��ł��o�����B���S�Ǘ��V�X�e������w�ϋɓI�ɉ^�p���邱
�ƂƂ����B
�@�@�s���S�s���̖h�~�ƈ��S���y�̊m��
�@�� 1�@�q�C�P�����ɂ�������S���y�̊m����}�邽�߁A���S���y��
�@�@�@�@�@�m���Ɍ������錾���s���ƂƂ��ɁA�C�t���x���Ȃǂ�������
�@�@�@�@�@�~�X��s���S�s����h�~���邽�߂̊����𐄐i����B
�@�� 2�@�q�����n�b�g�E���̎�����L�����W�E���͂���ƂƂ��ɁA�Z
�@�@�@�@�@�C�t�e�B�[�E�}�l�W�����g�E�V�X�e��(SMS)����w�ϋɓI��
�@�@�@�@�@�^�p���邽�߁A������ɒ��������w���S���i���i���́j�x��
�@�@�@�@�@�ݒu����ȂǁA���S���i�̐�����������B
�A�@��g�`�[���̋@�\����
�@�� 3�@��g�`�[���̋@�\���ő���ɔ��������邽�߁AOJT�ABTM����
�@�@�@�@�@��E���C���e������������ŁA���̐V���ȃv���O����������
�@�@�@�@�@���A���₩�Ɏ��{����B
�@�� 4�@����E���C���ɂ��A��Ƃ��Čo���N�����d����������܂�
�@�@�@�@�@�̐l���Ǘ����A�\�͂�K���̕]���܂������̂ɕς����
�@�@�@�@�@�Ƃ��ɁA���N�Ǘ��Ɉ�w�z���������̂Ƃ���B
�B�@���ォ��̎x���̐��̋���
�@�� 5�@�䕗�̐ڋ߂ɍۂ��ẮA�D���Ƃ̑䕗���̋��L��}��Ƃ�
�@�@�@�@�@���ɁA�t�F�C���E�Z�C�t��̊ϓ_����D���̑䕗��v��
�@�@�@�@�@�𗤏㑤���c�����A�K�v�ɉ����ď������邽�߁A���㑤�ɑ�
�@�@�@�@�@����x���`�[���i���́j��ݒu����B
�@�� 6�@�䕗�ڋߎ��̊e�n�𔑒n�������W���A�����̋��L���Ƃ�
�@�@�@�@�@��������B
�@�� 7�@���S�^�q�𑣐i���邽�߁A�D���ԏ��ʐM�l�b�g���[�N���[
�@�@�@�@�@����������B
�C�@�䕗��w�j�i���́j�̑��₩�ȍ쐬
�@�� 8�@�䕗��̊�{�I�l�������荞�ނƂƂ��ɁA���ԑD�Г�
�@�@�@�@�@�ɂ�����䕗���C��R�����̑䕗�C��ɌW�钲���E����
�@�@�@�@�@���ʂ������f�����䕗��w�j�i���́j�𑬂₩�ɍ쐬����B
�D�@�ً}���Ԃ�z�肵�����K�̏[���E����
�@�� 9�@�C��ۈ����ȂǑ��@�ւƂ̘A�g��������ɓ���A�@�߂Ɋ��
�������≉�K�Ɍ��炸�A�l�X�ȋً}���Ԃ������O���킸��
�@�@�@�@�@�����邱�Ƃ�z�肵�����K���[���E��������B
�@���̂ɑΉ������I�m�ȑ�ł���Ǝv����B����͂��̎��s�����҂�
��邪�A���݂܂ł̑���{�͎��̂Ƃ���ŁA���������e����
�ɐi�߂��悤�ƂĂ��Ă���ƕ����y�ԁB
�i�P�j�����P�V�N9��26���@�@�e���K�D�̊����E���ꓯ���W�����������A
�@�@�@������������S���y�m���Ɍ��������S�錾�����B���̂�
�@�@�@�����Ȃ����߁A10��20���������ɂ�����u�C���ۑ䕗�C��̂̓��v
�@�@�@�Ƃ��A���N�������܂ޏT�Ԃɂ����Ď��̂����r���[���A�ً}�Ή�
�@�@�@�P�������W���I�ɍs�����ƂƂ����B
�i�Q�j���N�@10��20���@�@�䕗��w�j�i�g�Y���͂ɌW�鎖���A�C��R��
�@�@�@���f�[�^�A���ԑD�Ђ̑Ή����ᓙ���܂ށj���쐬�A�e�D�ɔz�z�����B
�@�@�@�������܂ޏT�ԂɁA�e�E�������̂����r���[����ƂƂ��ɁA�����
�@�@�@�D������̂ƂȂ��ċً}�Ή��P�������{�����B
�i�R�j���N�@12��1���@�@������ɒ��������u���S���i���v��ݒu���A���S
�@�@�@���y�m���Ɍ������������J�n����ƂƂ��ɁAISM�R�[�h�Ɋ�Â��F��
�@�@�@��18�N�x���Ɏ擾���邱�Ƃ�ڎw���Ď葱�����J�n�����B
�i�S�j�����P�W�N4��1���@�@ �𔑒n�������܂Ƃ߂��f�[�^�x�[�X���\
�@�@�@�z���A���̊��p���J�n�\��B�������lj����[����}��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���ӁF�R��S��j
�@���̗��N�̉Ăɒ����V���������̎��K���ɑ����ނ��s���Ă���[18]�B
�����ǂނƁA�m���ɂ��̎��̂͑����ȃV���b�N�ł��������A���������
�����̖����o���Ƃ��ĊC�̐��E�Ŋ撣���Ă���Ƃ����Љ�ł������B����
��ǂݔ��Ɉ��g�����v��������B���̂܂Ƃ߂����݂��M�҂�́A�V����
�Ⴂ�͂��邪���D�u���{�ہv�A�u�C���ہv�ɂ�鉓�m�q�C���܂߂���D��
�K�̌o���҂ł���B��X�́A���̔��D���K�ɂ��o�����A���̌�̐l����
������傫�ȍ��Y�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��A�l�X�ȋǖʂŎ���������̂ł���B
�M�҂͊w�Z���ƌ�ɏ\���N�̗���E�ł��������A���D�ł̌o���͗l�X�ȏ�
�ʂŐ������ꂽ�����������Ă���B�����āA�ŋ߂ɂȂ菤�D�w�Z�̋���E
�Ƃ�������ɂȂ�A�����̋����q�B�����l�̔��D���K�ɗ������́A�u��
�ɂ������Ȃ��B�̐l���̃s�[�N�ɂȂ鎞�Ȃ̂�����A���ł��z�����Ċ撣��
�Ă����I�v�Ɗ��S�������đ���o���A�܂��A���������w���������܂�����
��A���Ă��邱�Ƃɔ��Ɋ������������̂ł���B
�@�������A���R�̎��Ȃ���D�̐��E�͈��S�ȍq�C����ł͖����B�M�҂�
�������D��w�ɏ��a58�N�ɓ��w��(�q�C�w��35��)�A�J�b�^�[���֏�����
�Ă����B���̃J�b�^�[���ł́A���N�̏t�x�݂ɂ͐�t����[���ɂ��铯��
�̕x�Y�ՊC�������K��ō��h���K���s���Ă����B�M�҂���w��1�N������Q
�N���ɂȂ낤�Ƃ��Ă���t�x�݂ł��������A���̎��ɓ��������h���s����
�����E�C���h�T�[�t�B�����D��̊w�����C����K�ʼn��ɏo���܂܍s���s��
�ɂȂ�Ƃ��������Ԃ��������B���ʂƂ��āA���̊w���͈�ӂ̕Y���̌��
���D�ɋ~�����ꖳ���ł������B�����A�M�҂́A�܂���w�N�ł���A������
���Ȃ��Ă���̂��S��������Ȃ���Ԃł������B�����āA���̎����̓^��
�ɂ��Ă͓�������̍q�C�w�ȋ����̊����א搶(���݁A���喼�_����)��
�C�Z�҂̎��_���猩���ڍׂȃ��|�[�g���܂Ƃ߂Ă�����[19]�B�����ł́A
�����̎��n��I�ȋL�ځA���̎��̋C�ۊC�ۂ�{�����@�ɑ���l�@������
����������Ă���B�܂��B���������������N���������́A���K�D�⎖���X
�^�b�t���܂߂��W�҂̑g�D�I�ȑΉ��̗L������������Ă���B�M�҂͏�
�D��̍��w�N�ɂȂ�A���̃��|�[�g�����߂ēǂ�ŁA���̂��N�������ꍇ
�ɂ͂����ɗ�Â��I�m�ȁA�����đg�D�I�ȑΏ����d�v�ł��邩�A�܂���
�̋L�^���c�����Ƃ̏d�v����Ɋ��������̂ł���B�����搶�́A���̃��|
�[�g�̍Ō�Ɂu�������D��w�́A�C�̑�w�ł���B����Ƃ��A���Ƃ��邢
�͉ۊO�����ŁA�傢�ɊC�ɐe����ł��炢�����B�����A����Ƃ͈قȂ��
�ꐫ�E�댯���̂��邱�Ƃ���ɖY��Ȃ��łق����Ɗ���āA���̕��͂���
�����߂��B�v�ƋL����Ă���B���������L�^���A������̂��߂Ɏc������
���ɏd�v�ł���Ɗ�����B���́A�M�Ҏ��g���C��̌o���҂ł���B����
���D��w�̃J�b�^�[���ł͉ċG�̓`���s���Ƃ��āA�s���l�X�ɂ�鑊�͘p
�̔������q���s���Ă���B�M�҂͏��a63�N��4���Ɂu���{�ہv�̎��K���I��
�āA�������D��w�̑�w�@�֓��w���Ă����B�����ŁA���̔N�̏��q�ɎQ��
���Ă������A�ɓ������̔�����`������`�������r��A��������2�C��
�ŋ����ɂ������A20��������D���Ă����J�b�^�[��]�������Ă��܂���
�̂��N�����Ă��܂����B���ʂƂ��āA��2���Ԃ̕Y���̌�ɒn���̋��D�ɋ~
������A�S���������ł���A�厖�ɂ͎���Ȃ������B�����ŁA�����ŏ㋉
���ł���A�w���I����ɂ������M�҂Ƃ��Ă͑����ɂ炢�v������������
�ł���B�������A���̎��ɂ͐�̊����搶�̃��|�[�g����K�D���K�Ŋw��
���A�܂��͍őP�ȑΏ����s�����ƂƁA��y�B�𖾂邭��܂����ɋ߂��B
���̌�A��������P�Ƃ��ׂ��A��w�@�݊w���ɐ}���ق̊C��֘A�̏��Ђ�
�����ɓǂ��������̂ł���B����́A���̌�̗���E�A�܂����݂̏��D
����E�ɂ����Ă��A�傫�ȍ��Y�ɂȂ��Ă�����̂ł���B�����ŁA�M�҂�
�傫�ȉ����́A�����ŏЉ���Ē������쓇���⊪���搶�̂悤�ȁA����
�̌o�߁A�N�����������ɑ��镪�́A�����Ĕ��ȂƏ����ւ̒E�E�E�A
�����������̂�ԗ������ڍׂȕ��c���Ă��Ȃ����Ƃł���B�u���K��
�D �听�ێj�v[20]��ǂނƁA�����̏�������n�܂������D���K�́A���ɂ�
�傫�ȋ]�������A�ꓬ�̗��j��m�邱�Ƃ��o����B�����āA����ɂ�
�����ɏ�ɑO��ڎw�����̑�Ȑ�y�B�ɑ傢�Ɍh�������Ē������B
�M�҂�̖ڂ̑O�ŋN�������}�U�[�V�b�v�ł���u�C���ہv�̍��ʎ��̒���
�ɁA���ۂ̌�����ԋ߂Ɍ��āA�~���������x�����ď�g������K���Ɗԋ�
�ɐڂ�����X�ɂ́A��X�̎��_���猩���A���������ڍL�^���܂Ƃ߂�`
��������Ɗ����鎟��ł���B�ǂݕ��ɂ���ẮA�q�C�P������ӂ߂��
�����悤�ɑ������邩������Ȃ��������ł͂Ȃ��B�u�P�D�͂��߂Ɂv��
���q�ׂ��悤�Ɏ��̂͐ӂ߂ĂȂ��Ȃ���̂ł͂Ȃ��B���S�^�q�������铯
���Ƃ��ẮA�M�҂�̈ӋC�Ɩڎw�����������������B
�@�Ō�ɖ{�_���܂Ƃ߂�ɓ�����A�x�R���D�������w�Z���_�����̋g�c
���O�搶����͑����̋M�d�Ȃ��ӌ����܂����B�܂��Вc�@�l�C�m��
�x�R�x���A�x�R���D�������w�Z�̊F�l�ɂ͑����̗�܂��ƋM�d�Ȃ��ӌ�
���܂����B���Z�Z�p�E���̎R���b���A�Y�b���Ď��ɂ͎����쐬�y��
���͍\���ɂ��s�͂��܂����B�܂��x�R�n���C�ۑ�A���ؕx�R�`�p����
������͋C�ۊC�ۂ̃f�[�^�A�����V���x�R�x�ǂ���͎��̎��̎ʐ^�̂���
���܂����B�����Ɍ������\���グ�܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���� ��t�@���j
[1] �C�ے�HP�Fhttp://www.jma.go.jp/jma/index.html
[2] ����ׁA���V�P�v�A�Γc�A�F�u�䕗0423���ɂ��C���ۊC��̋C�ۏv�A
���{�q�C�w��2005�N�x�H�G������E�C�m�H�w������A����17�N10��
[3] �x�R�n���C�ۑ�HP�Fhttp://www.tokyo-jma.go.jp/home/toyama/
[4] �쓇�T�F�u�ɐ��p�䕗�Ƃ̎�����\�l���ԁv�A�D�ƋC�� ��178���A
(��)���{�C�ۋ���A����5�N1��
[5] �쓇�T�F�u�ɐ��p�䕗�Ƃ̎�����\�l����(��)�v�A�D�ƋC�� ��179���A
(��)���{�C�ۋ���@�A����5�N7��
[6] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.172�A���R�����X�A����11�N12��
[7] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.174�A���R�����X�A����11�N12��
[8] �i���j���{���H����u���{�ߊC1000m���b�V���f�W�^���f�[�^ �k�C���E
���k�C��v
[9] �g�c���O�F�u�x�R�p�̊C��Ɗ����g�v�C(�L)���{�C����C1987�N8��
[10] http://wxw.miyazakycom.com�F(��)I.B.C�^�{��}�C�R���V���b�v �z�[���y�[�W
[11] �\�E�q��F�u�V�����C�m�Ȋw�vpp.177�`178�A���R�����X�A����11�N12��
[12] ���ؕx�R�`�p������HP�u�g�Q�ϑ����v�F
�@�@ http://www.pa.hrr.mlit.go.jp/toyama/harou/harou.html
[13] �C�ƈ��S�F�u���{�C��h�~����v�C2005.No.525
[14] �u���{�C�����C���v�`�p�ɂ�����d���D���̈��S��Ɋւ��钲������
���v�C���{�C�C��h�~����C����10�N3��
[15] �u���{�C�����C��ɂ�����𔑒n�y�ѕd�����@�Ɋւ��钲���������v�C
���{�C�C��h�~����C����14�N3��
[16] �C��ۈ������H���F�u�{�B�k���ݐ��H���v
[17] �u�C���ۑ䕗�C��̂ɌW��Ĕ��h�~��ɂ��āv�F�Ɨ��s���@�l �q�C
�P����HP�Fhttp://www.kohkun.go.jp/accident/new_action.html
[18] �u�C�ɐ�����@�C���ێ��̂��ꂩ��v�A�����V��(�x�R��)����16�N10��
[19] �����ׁF�u�E�C���h�E�T�[�t�B�����̂ɌW�镪�́v�A�������D��w��w����
����裑�23��,���a59�N10��
[20] �听�ێj�ҏW�ψ���F�u���K���D�@�听�ێj�v�A���R�����X,���a60�N10��